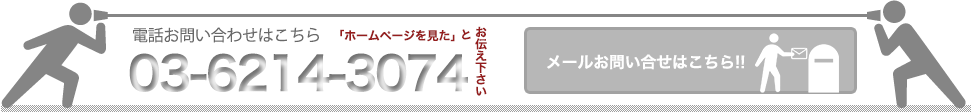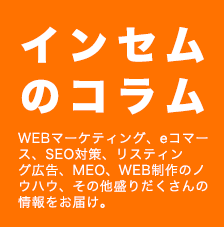絶対来る!WEBマーケティングInstagram
ども、カップラーメン大好きWEBマーケティング担当Dです。
外食の際はつけ麺派ですが何か?
絶対来る!WEBマーケティングInstagram
と、大きな声で言ってみましたが、Instagramってどう使うの?なWEBマーケティング担当Dです。
ただ、最近の10代は特にInstagramで検索らしいです。
※20代前半は特にtwitter検索(過去記事参照)
前回記事でもとりあげましたが、通常検索(GoogleやYahoo!)と肩を並べる、もしくはそれ以上にtwitterやInstagramでの検索が普段使いされています。
検索のされ方が変わってきた?ググるって古いって言われましたけど・・・
つまり、これからの世代にアプローチしたい場合はSNS(twitterやInstagram)は必須!
特にInstagramは伸び率が半端ない状況だという事。
なぜ、Instagramなのか?
写真大好き日本人!
子供の思い出を残す為の写真を親が撮影
誕生、日常(特に初めてシリーズ)、入園式、七五三、遠足、卒業式、etc
遠足などはカメラ屋さんが撮ってくれて、学校の壁に貼りだされて購入するパターンでしたね(好きな子とさりげなく一緒に写っている写真を隠れて購入するっていうあるある)
自分たちの思い出を残す為に写真撮影
林間学校、修学旅行、旅行、etc
インスタントカメラを修学旅行に持っていって、窓越しにインスタントカメラを叩いてフラッシュ合戦をした記憶があります(フラッシュを上手く出すコツとかあって下手な人は撮った写真が現像した時にボケちゃってるっていうあるある)
そんな写真好きな日本人がスマホという神器を持った事により、フィルムの枚数を気にすることなく、どこでも写真が撮り放題!(インスタントカメラ24枚撮りで撮影していて、最後の方の一番撮っておきたい写真をフィルムが足らず撮れずに悔しがるっていうあるある)
でも、よく考えてみたら、
Facebookやtwitterでも写真あげれるじゃん!
そうなんです!そこがSNSをフル活用すべきポイントなんです。
Instagramは写真に特化させている為、Instagramで上げた写真に一言添えてtwitterとFacebookに連動。
こうする事で各SNSの長所を活かし・短所を補う事ができるというメリットが。
※写真にハッシュタグを付ける事が重要です(#インスタントラーメン)←こんなの
各SNSの使い方
・Instagramは拡散性は無いので、#ハッシュタグを付けてもらい巻き込み型のキャンペーン
東京ディズニーランドなどのテーマパーク系やスターバックスの様な飲食系はすでに行っていますね。
・twitterは自然検索にも対応しているので、文字数と#ハッシュタグを利用し拡散
・Facebookは繋がりからの拡散
また、みなさんがお好きなSEO対策上、SNSとの連動は極めて重要だと付け加えておきます。
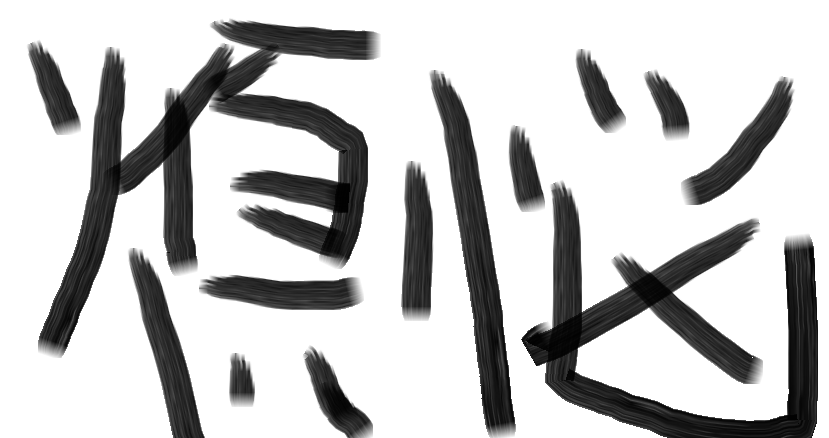
【裏技】SEO1位確定!外部リンクを使わない内部リンクSEO対策
WEBマーケティング担当Dです。
本日より新しい女子社員も増え、燃えに燃えているインセム男性社員。
WEBマーケティング担当M氏は「これだから男は・・・」と隣でぼやいています。
余談はさておき、本日とうとう弊社SEO対策チームより大きな報告が上がってきました。
SEO対策は内部リンク108本と外部リンク1本で生成する事により自然検索結果1位を瞬間的に取れる!(ただしGoogleに限る)
一瞬とはいえ、外部リンクに頼らない方法でSEO対策の結果1位を生み出せたのである。
今後は、2通りの事が考えられる為、実験チームを新たに発足させ検証していきます。
-----------------------------------------------------------------------------------------------
■第一陣
SEO対策瞬間起爆増幅拡大チーム(通称:SEO対策Bチーム)
※一瞬に全てを掛け、どのタイミングで1位を取れば有効かを検証する事が目的
■第二陣
SEO対策継続力増幅赤色チーム(通称:SEO対策Aチーム)
※継続力を高める為に赤オーラでの継続率を検証する事が目的
-----------------------------------------------------------------------------------------------
では、なぜ内部リンクなのか?108本なのか?
皆さんも疑問に思ったであろう。
・内部リンクである事。
・108本である事。
この条件に辿り着いたのは、まことしやかに囁かれているGoogleの人工知能化である。
Googleが人工知能を持つことによりゆくゆく世界はGoogleに制圧されるであろうと・・・。
Googleの世界制圧を阻止すべく昨今ではGoogleの”ググル”に対抗し、
twitter検索による”とうぃとぅるー”が躍進している。
Googleの人工知能化を考えた際に人間にありロボットに無いものは何か?
Yes!煩悩!!!
弊社SEO対策チームのY氏が「煩悩ちゃいますか」と飲み会で呟いたのがきっかけだった。
人間の煩悩108つ。内に秘めたるもの、内部リンク。
そこから苦節3日で辿り着いた結果が、
SEO対策は内部リンク108本と外部リンク1本で生成する事により自然検索結果1位を瞬間的に取れる!(ただしGoogleに限る)
今後も弊社SEOチームは毎日飲み会開催を行い、煩悩と戦っていく事になるであろう・・・続く
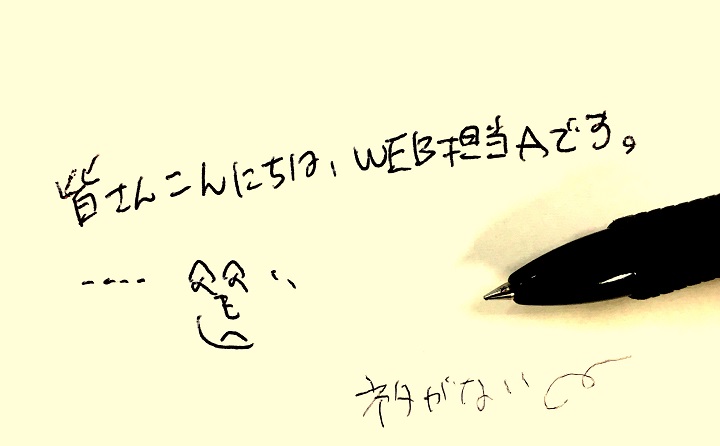
記事のネタがなくて悩んでいるすべての人へ
WEBマーケティングの一環で、社内で記事を書かなくてはいけない。
毎週ブログを書くことを義務付けられている。
でも、手が回らない、後回しになる。
やろうと思っても、後回しになる。
自社サイトを有効活用しようとして、検索順位とかを上げようとして、更新が必須だということも知っていて、上記のような状況に陥っているWEB担当者の皆さんこんにちは。
WEBマーケティング担当Aです。
今日は僕が記事を書くときに使っている定跡をご紹介します。
正直言って、記事を書くことはそんなに難しい事ではありません。
よく「ネタがすぐに尽きてしまう」というご相談を受けますが、少し見方を変えてみるとネタはそうそう尽きません。
以下パターン別にご紹介します。
①事例パターン
これは簡単です。よく工事業者さんのブログなどでも使われているパターンですね。あらゆる業種に応用できます。
例えば、例として「エクステリアの改修工事の事例」を考えてみましょう。
・どんな悩みを持って相談を受けたのか
・それに対してどのような改善案を提示したのか、なぜその改善案だったのか
・実際にどのようなエクステリア工事になったのか
・なぜ最終的にそのようにしたのか
(・完成後の結果クライアントからの反応がどうか)←お客様の声があれば。
といったイメージです。
要は実体験を順を追って記載していけば良いだけです。
②1つのテーマへの帰結パターン
これも意外と簡単です。物事を構成する事象を細分化して1つのテーマに帰結させます。
ちょっと言い方が抽象的ですね。具体例で見てみましょう。
例えば「インセムコラム」。WEBマーケティング担当Aの記事は基本的には「WEBマーケティング」という1つのテーマに帰結しています。
ただ、「WEBマーケティング」自体は巨大なテーマであり、その中に「SEO」「PPC」「ECサイト」「MEO」「SNS」「Youtube」「LP」「HP制作」など様々なカテゴリーが存在しています。さらにそのカテゴリーもさらに細分化できて、例えばSEOであれば「コンテンツSEO」とか「BtoC向け業界のSEO」とか「内部対策重視のSEO」とか「SEOに効果的な外部対策」とか沢山の構成要素に分かれています。要は、大きなテーマに沿って考えるよりも、自分が身近に接している1つ1つの構成要素を見直してあげることで、ネタは驚くほどたくさんあります。
③統計・数字を絡めるパターン
国から出ている白書や転載可のデータがあること前提ですが、数字を絡めた記事も書きやすいです。
例えば、「スマホの利用者数が増えている」という1つの統計値に着目したとします。
そこに対して、その背景、マーケットの変化、これから考えられること、その為に今準備出来ることなどを1つ1つ考察すればオリジナル記事の完成です。
アンケート等を自社で取っている場合などは、活きたデータが手元にある訳ですからそれを利用しない手はありません。
あと、基本的なことですが、「例えば」という形で一般論を身近な例に言い換えることも非常に重要です。このコラムにおいても既に「例えば」が5回使われています。
ちなみに、この「記事のネタがなくて悩んでいる全ての人へ」自体はどのパターンに当てはまるでしょうか。そう、②ですね。「WEBマーケティング」というテーマの中の「SEO」のカテゴリーの「記事を更新」という内容について記載しています。
是非、明日からの記事ライフの参考にしてください。
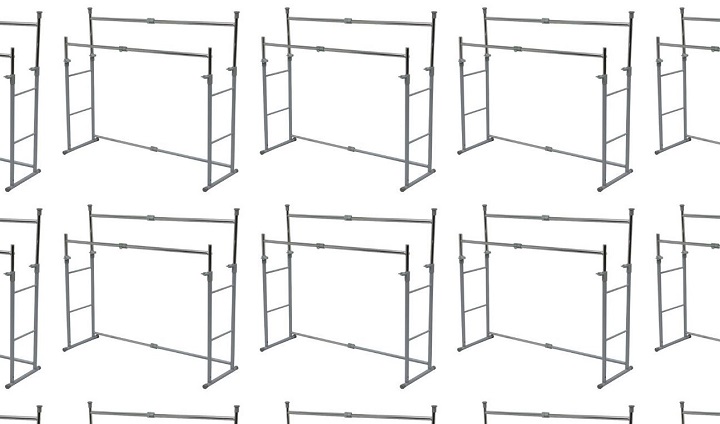
WEBマーケティングコラム番外編『押入れハンガーを買った』
私事ですが、最近もっぱらDIYに精を出しています。
・開閉式の扉が壊れてしまったので修理をする
・玄関のドアの立て付けが悪くなってしまったので修理をする
・収納が足りなくなってしまったので押入れを改造して収納を増やす
・調味料が増えすぎて置き場所がなくなったので棚を作る
・ベランダのウッドデッキが割れたので板を差し替える
・ベランダの日よけが風でなくなってしまったので修理する
・靴の収納が足りなくなったので靴棚の段を増やす
いつ終わるとも知れない、ボロボロの我が家を週末直したり、手を加えたりしている訳です。
もちろんDIYとは言え、そこには消費が発生します。
ペンキを買ったり、釘を買ったり、つっかえ棒を買ったり、蝶番を買ったり、様々です。
ではその消費をする際、どのような経緯を辿っているのでしょうか。
アナリティクスではうっすらとしか見えない、ユーザー消費行動を見直すことで、販促マーケティングのヒントが見えてくるかもしれません。
n=1なので、参考になるかはわかりませんが…
今回は先週末の事例として、
「収納が足りなくなってしまったので押入れを改造して収納を増やす」
ということにフォーカスしてみます。
悩み:
・洋服が現状の収納に入りきらず、リビングやソファに畳んで置いてある
・現状の収納は大きめのタンス×2
・タンスがパンパンで、取り出したり、入れたりするのに毎回労力がいる
要望:
・本来収納スペースじゃないところの洋服をなくしたい
・タンスをスムーズに使いたい
・着替えの動線を短くしたい
■「洋服を捨てる」VS「収納ボックスを増やす」
まず考えたのは「洋服を捨てる」VS「収納ボックスを増やす」ということです。
洋服の大半は妻のものです。
ダメもとで聞いてみました。
「この辺の洋服、今流行りの断捨離してみない?」
ダメでした。
よって、「洋服を捨てる」線は無くなります。
「収納ボックス増やす」しかない訳ですが、問題はどこに増やすかです。
■「リビングに増やす」VS「押し入れに増やす」
大きな家ではありません。
リビングにタンスを増やしてしまったら、居住スペースが圧迫されます。
「この場所に置いたらどうだろうか」
「むしろベランダを簡易的に防風防塵してそこに置いたらどうだろうか」(「ベランダ改造 部屋」で検索)
というような思考を辿り、行きついた結論が、「押し入れに増やす」というものでした。
昔ながらの横幅180×奥行90×高さ170程度の押入れです。
押入れの中はさらに高くなっており、200くらいあります。
なんとなく物を詰め込んでいたのですが、どうも隙間が多くて、具合が悪い。
一度押入れの奥にしまい込んでしまったら、しばらく取り出す気も起きないイメージです。
「押し入れの中に上手いこと洋服を収納するスペースを作れるのではないか」
それからネット検索の開始です。
「押し入れ収納」

「押し入れ収納 洋服」

検索結果で何が目立つでしょうか。
そう、画像です。
最近のGoogle検索では、Googleショッピングの検索結果、画像検索結果が自然検索結果に表示されることが多くなりました。
これは便利ですね!
今一つイメージが沸かないとき、画像が出ると、
「そうそうこんな感じ!」
「あ、こんなのもあるんだ!」
とイメージが具体化されます。
WEBマーケティング的に考えると、狙っているキーワードで実際に検索した時、どんな感じで検索ユーザーがその情報を見始めるのかを確認、意識しておくことは重要かもしれませんね。
画像はサイトへの誘導にも繋がっています。
Googleショッピングの画像は購入画面に繋がるだけですが、画像検索の画像は、その画像が使われているサイトやブログへの誘導が多いです。
最近自社サイトでブログの更新等が声高に言われている理由にも関係してきますね。
僕なんかは意外と画像検索からサイトへ流入している場合が多いです。
今回の場合は、イメージを具体化させた上で、主にブログを見ていました。
ブログアフィリエーターさんのターゲットですね。
家ではPCで、通勤中にスマホで。
「こんなのどうだろう」
「このサイト面白そう」
妻との情報共有は主にLineです。
Lineを送るボタンを多用します。
※Lineで送るボタンを設置する
https://media.line.me/howto/ja/
■買うものは決まった。「じゃあ何どれを買う?」
押入れ収納のイメージが固まったら、購入です。
今回は押入れハンガーの購入をすることにしました。
ちなみに「押入れハンガー」という言葉は始めから知っていたわけではなく、検索の中で初めて知った言葉です。
実際にどのくらいの大きさなのか、質感はどうなのか、
ネット購入の際は現物を見る事ではないので、初めて買うものは何を買うにしろ不安になります。
そこで活用したのが、口コミです。
~早く届いた
~丈夫だった
~簡単に組み立てられた
~すぐ壊れた
色々な口コミがありますが、良いことが書いてある口コミは購入の後押しになります。
ECサイトで商品を販売している場合は、口コミを一覧にするのももちろん良いですが、どんな意見が多いのか?といったことを「口コミまとめ」みたいにしてあげるとより良いかもしれません。
例えば、
「口コミ投稿者の80%の方が『丈夫だった』と言っています」
「口コミ投稿者の75%の方が『コスパが良い』と言っています」
とまとめてあげれば、丈夫さを求めている人やコスパを求めている人の目に留まるはずです。
結局、僕は口コミをぱらぱら見ながら、「この商品だったら大丈夫そうかな」と思い、購入に至りました。結果はGreatでした。
■まとめてみると
今回の購入に至るまでの経緯を簡単にまとめてみましょう。
①生活に不自由を感じ何か良い方法はないかとWEB検索
②画像をみて「なるほどこういう方法があるのか」と思い、主にブログで使い方を確認
③Line共有機能を使い、妻と情報を共有
④何を買うかの方向性が固まる
⑤検索中に知った商品キーワードで検索(今回は「押入れハンガー」)
⑥同じような商品が多数あったが、主に口コミを見て購入(今回は「丈夫」なものを探していた)
以上です。
では、この流れからどのようなWEBマーケティング手法が考えられるでしょうか。
今回のポイントとしては、
・写真
・ブログ
・Line共有機能
・口コミ
ですね。
よくWEB担当者から「ブログ、何かいたらいいかわからない、ネタがない!」という相談を受けますが、特に今回のようなエンドユーザー向けの商品を扱う場合には、利用実例などは格好のネタになりますし、SEOなどを考えた場合にもプラスですし、なにより、ユーザーに有益な情報を与える強力なツールです。
写真も面倒かもしれませんが、一工夫加えるだけで、サイトへの流入経路を一つ増やすことになりますので、是非加えたいところです。
上記内容はWEBマーケティングとくくられますが、考えようによっては先般記事にしたデジタルマーケティングとも密接に関わってくる内容です。
今は「PPCだけ」「SEOだけ」といった施策ではなかなか効果が出しづらくなってきています。それで悩んでいる会社さんもたくさんいらっしゃいます。
だからこそ…ですね。
以上です。
Googleモバイルフレンドリーアルゴリズムが実装
モバイルフレンドリーはどのくらい重要なのか
周知のとおり、2015年4月21日からGoogleモバイルフレンドリーアルゴリズムが実装されます。
will have a significant impact in our search results
とGoogleの発表にあるように、大きな変動を引き起こす可能性があります。
端的にいうと、「スマホ対応していないサイトはスマホ検索での順位が下がります。しかも可能性大。」といういう内容です。
スマホ対応といえば、2013年夏には、
Googleアドワーズ広告でエンハンストキャンペーンが強制導入されたり、
Yahoo!プロモーション広告でユニファイドキャンペーンが強制導入されたりと、
結構、重い、変動がありました。
※エンハンストやユニファイドは、「マルチデバイス化に対応したキャンペーン機能」と総称されます。
要は、みんなスマホ、タブレット持ってるから、PCとかスマホとかタブレットとかの区別なく最適な広告出します、という内容です。
今回は自然検索です。
解析ツールなど見ていても、
「オーガニック経由多いなぁ」「スマホからの流入が増えたなぁ」「そもそもスマホの売上がPCの売上逆転したなぁ(ECの場合)」
というウェブ担当者の人も多いのではないでしょうか。
そうです。「スマホ経由のオーガニックからの流入」は意外と無視できない数になってきているのです。
もちろん「まだまだうちはPC>スマホ。スマホからのお問合せなんてないよ」という方もいらっしゃるかもしれません。
しかし、ユーザーのウェブの使い方は、マルチデバイスです。
例えば、不動産。
出勤時にスマホで物件を見る→昼休みにPCで物件をもう一度みて問合せる
という動き、多いです。
この場合、最初のスマホ検索の段階で露出が無かったら、お問合せもなかったかもしれません。
PCでも露出があって、スマホでも露出があって、というのは今の時代では必要最低限なことだと考えられます。
結論、ウェブから集客しようとしてる会社の大多数に対して、モバイルフレンドリーアルゴリズムへの対応は非常に重要ということになります。
ところで、スマホってみんな持ってるっていうけど、本当にみんな持ってるの?
統計局からデータを抽出しました。
■スマートフォンの利用率(日本,平成24年)
・スマートフォンの利用率は全体で52.8%と平成23年よりも約20ポイント増えた。(平成24年は32%)
・最も利用している20代87.9%。最も利用率が伸びたのは40代で、28.8%→58.8%。
・他、30代、10代においても約30ポイント増加。
<まとめ>
スマートフォン(平成24年→平成25年)
全体:32.0%→52.8%
10代:36.7%→63.3%
20代:68.4%→87.9%
30代:49.0%→78.7%
40代:28.8%→58.8%
50代:13.7%→32.4%
60代:4.7%→8.7%
一方、日本の総人口は1億2729万8千人です。(平成25年10月)
全体の数値を取って、
1億2729万8千人 × 52.8% = 約6700万人
がスマホを持っていることになります。
結論:みんな持っているわけではないです。
スマートフォンは日本人口の過半数が持っていることになります。
しかし、例えばスマホ広告を考えて、そのターゲットが10代~50代だった場合、その数値は凡そ70~80%に上がります。
これは十分に巨大なマーケットになり得るのではないでしょうか。
スマホ対応を検索順位ランキングの要因にするとGoogleが公式発表
スマートフォン(モバイル)ユーザーに、より良い検索結果を。
Googleは2015年2月26日(現地時間)に、スマートフォン対応をモバイル検索順位に影響するアルゴリズムを、
2015年4月21日から世界中で一斉に開始すると発表しています。
Googleウェブマスターツールブログ参照
本文の中で”サイト全体のモバイルユーザビリティの改善”とGoogleはうたっています。
近年はPCでの検索よりもスマートフォンでの検索が増えていることからの判断と考えられますね。
Googleは2014年11月19日にも、ユーザーが目的の情報をより簡単に見つけることができるようにするために、
モバイル版の検索結果に [スマホ対応] というラベルを追加していました。
※上部画像の検索結果部分
WEBマーケティングを行う上でも、スマートフォンユーザーへのアプローチは必須だと感じています。
この発表にBtoC(消費者を相手にしたサービス)の商売をされている企業は危機感を持っているかも。
BtoB(企業向けのサービス)の企業でも、モバイルの検索結果に影響があるとなれば、
スマホ対応を検討しても良いかもしれませんね。
スマホ対応のホームページはお持ちですか?
Googleが検索結果の要因について、ここまでハッキリと公言したのは初めてかもしれません。
それだけ検索結果に大きな影響が出る事が予想されます。
約2か月後の発表をしたのは、スマホ対応(ホームページ制作・スマホレスポンシブ対応)の
準備期間を設けてくれたのかもしれませんね。Google先生、優しいです!
ホームページのURLがスマホ化OKかは下記サイトよりチェックできます。
モバイルフレンドリーテスト
ユーザーが求めているコンテンツを増やし、
常に新しい情報を更新しているホームページが必要だと言われていますが、
+α(スマホ対応)も必要項目に加えてみてください。
SEO対策の具体的方法1
上位に表示させるために対応すべきこと
SEOとはサーチエンジンの検索結果のページの上位に自らのサイトを表示していくための対策のことです。自分のサイトで、他のライバルサイトを大きく上回るSEO効果を得るために最も大切なのは、他のどのサイトよりも役立つコンテンツを作成し、ユーザーに届けるということです。この目的に従って様々な手法を使っていきます。
検索エンジンの表示順位を決定する基準は数百にも及ぶと言われていますが、実際に上位に表示させるために対応すべきことはそんなに多くはありません。一番効果的なのは、ブラウザの上部に表示されるタイトルです。このタイトルの部分を、一番獲得したいユーザーに向けて最適化させます。
例えば文房具で上位に表示させたい場合、「文房具の店○○」と「文房具・雑貨・アクセサリーの店○○」では、前者の方が上位に表示されます。後者の方がキーワードが多い分、文房具の重みが減ってしまうからです。もし雑貨というキーワードでも表示させたい場合、「文房具」「雑貨」を同じタイトルに入れるのではなく、「雑貨」をタイトルに入れた別のページをつくることで両方のページを上位にすることができます。つまり「文房具の○○」と「雑貨の○○」別々のページをつくることで、それぞれの検索ワードで上位に表示させるようにするのです。
SEO対策はタイトルの工夫次第
タイトルをつける上で重要なのはできるだけキーワードを小分けして短くすることです。SEOにおいて一番簡単で効果的なのが、このようにタイトルを工夫することです。
他社のSEOの対策のレベルを見分けるには、このタイトルを見ることが一番手っ取り早い方法です。タイトルが長かったり、キーワードが多かったり、そもそも検索キーワードがタイトルに入っていなかったりすると、対策が充分でないということになります。逆に言えば、これと逆のことをすれば他サイトよりも上位に表示させることができるということです。
SEO、リスティング広告
SEOやリスティング広告の上位表示でユーザーを増やす
プレアクセス対策のひとつであるSEO、リスティング広告とは
ユーザーをサイトへ誘導するにはオンアクセスの工夫が必要ですが、このオンアクセスの段階でメインとなる手法がSEOやリスティング広告です。SEOとはサーチエンジンの検索結果のページ表示の上位に自分のサイトが表示されるように工夫することで、そのためのツールや技術のことをSEO対策と言います。
サーチエンジンは、登録されているwebページをキーワードに応じて表示します。その際の表示順位はそれぞれのサーチエンジンが独自の方法で決定しています。GoogleならばGoogle独自の方法で決定しているのです。言うまでもないことですが、表示順位が上に上がるほどユーザーの目につきやすく、訪問者も増えます。
具体的な方法としては、ターゲットに対するキーワードの選択を最適化すること、より多くのサイトにリンクしてもらうことなどの手段があります。しかし、サーチエンジンの表示順位を決定するアルゴリズムは日々高度化しているため、これさえやればいいという方法はありません。コンテンツを充実させて、様々な方法でユーザーへの認知を広げていくことがいちばん重要です。
時期などのピンポイント戦略にはリスティング広告
リスティング広告ですが、リスティング広告とは検索エンジンでユーザーが検索したキーワードに連動して表示される広告のことです。大抵の場合検索結果の上部や右側部分に表示されます。ユーザーは検索したキーワードに関する情報を欲しており、そのユーザーのうちの一部は商品の購入やサービスの利用に結びつきます。そのユーザーを獲得するための最も有効な手法がリスティング広告です。
リスティング広告の主な掲載媒体はヤフーのYahoo!プロモーション広告とGoogleのGoogleAdWordsです。リスティング広告はキーワード単位で選択して表示させることができます。そのため、ユーザーの興味関心にピンポイントでターゲッティングすることができます。